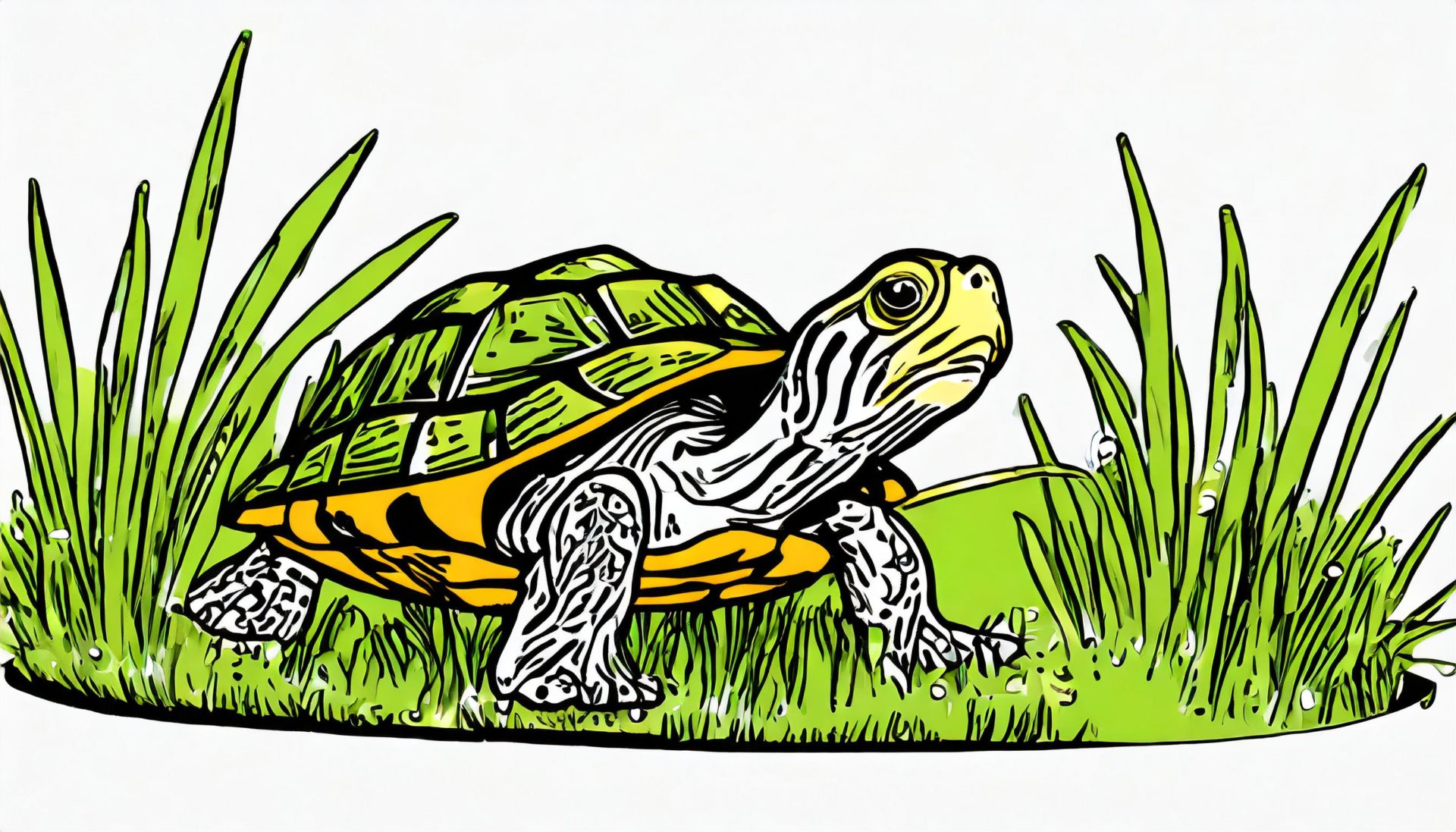ミドリガメの成体を正しく飼育するための知識を身につけよう!
ミドリガメ(ミシシッピアカミミガメ)は、ペットとして長年親しまれてきましたが、成体になると大きく育ち、適切な飼育環境が求められます。また、近年ではミドリガメの飼育禁止についても注目されており、「いつから禁止?」「なぜ規制されたの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、ミドリガメの成体の特徴や寿命、適切な飼育方法(室内飼育・必要なもの・おすすめの餌)を詳しく解説します。さらに、飼育禁止の理由や最新の規制情報についても触れています。
ミドリガメを飼っている方や、これから飼育を考えている方にとって役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
ミドリガメ成体とは?
ミドリガメの特徴と成体の見分け方
ミドリガメ(ミシシッピアカミミガメ)は、北米原産の水棲カメで、日本では長年ペットとして飼育されてきました。幼体の頃は甲羅が鮮やかな緑色をしているため「ミドリガメ」と呼ばれていますが、成長すると色がくすみ、黄褐色や黒っぽくなることが多いです。
ミドリガメの成体の特徴は以下の通りです。
- 体の大きさ:オスは約15~20cm、メスは約25~30cmと、メスの方が大きくなる
- 甲羅の色:幼体の頃の鮮やかな緑色が薄れ、暗い色合いに変化する
- 耳の後ろの赤い斑点:この模様が特徴的で、ミシシッピアカミミガメの見分けポイント
- 性別の違い:オスは爪が長く、しっぽが太くて長い。メスは甲羅が大きく丸みを帯びている
ミドリガメが成体になるまでには、約5~7年かかります。成長すると飼育スペースや水質管理が重要になるため、しっかりと環境を整えることが大切です。
ミドリガメの寿命|ギネス記録は何年?
ミドリガメの平均寿命は20~30年とされていますが、適切な環境で飼育すればさらに長生きすることもあります。野生では外敵や環境の変化によって寿命が短くなることが多いですが、家庭でしっかり管理すれば長生きしやすいのが特徴です。
世界最長寿のミドリガメは何年生きたのか?
ギネス世界記録として正式に認定されたケースはありませんが、報告されている最長寿のミドリガメは40年以上生きたとされています。国内外では「飼っていたミドリガメが50年以上生きた」という話もありますが、正式な記録は確認されていません。
ミドリガメを長生きさせるポイント
- 適切な水質管理:こまめな水換えとフィルターの使用で清潔な環境を維持
- バランスの取れた食事:カルシウムを含む餌や野菜を取り入れ、偏りのない食事を与える
- 日光浴や紫外線ライトの使用:甲羅の健康維持のため、紫外線をしっかり当てる
- 広い飼育スペースの確保:運動できる環境を整え、ストレスを軽減
ミドリガメの寿命を伸ばすには、**「水質・食事・紫外線・運動」**の4つが重要です。適切な飼育環境を整えることで、ペットとして長く付き合っていくことができます。
ミドリガメ成体の飼い方
室内でのミドリガメの飼育方法
ミドリガメの成体は大きく成長するため、室内で飼育する場合は十分なスペースを確保することが重要です。また、水質管理や紫外線対策を怠ると病気の原因になるため、適切な環境を整えましょう。
① 飼育スペースの広さ
ミドリガメは活動的なカメなので、狭いスペースではストレスが溜まります。
- 最低限必要な水槽サイズ:60cm(小型個体)~120cm(大型個体)
- 水深の目安:甲羅の長さの2倍以上(泳げる深さが理想)
- 陸地スペース:甲羅干しできる場所を確保
② 水質管理のポイント
ミドリガメは水を汚しやすいため、適切な水質管理が欠かせません。
- ろ過フィルターの設置:強力な外部フィルターを使用
- 水換えの頻度:週に1~2回(全換水は月1回程度)
- 水温管理:25℃前後を維持(冬場はヒーター使用)
③ 紫外線とバスキングライトの設置
ミドリガメの健康維持には、紫外線が不可欠です。
- 紫外線ライト(UVBライト):甲羅の健康維持とカルシウム吸収を促進
- バスキングライト(保温ライト):甲羅干し用の陸地を温める(30~35℃推奨)
ミドリガメ飼育に必要なものリスト
ミドリガメの成体を飼育するために、以下のアイテムを準備しましょう。
| 必要なもの | 理由 |
|---|---|
| 大型水槽(60~120cm) | 十分な泳ぐスペースを確保するため |
| ろ過フィルター | 水を清潔に保ち、水質悪化を防ぐ |
| 紫外線ライト(UVBライト) | ビタミンD3の合成を助け、甲羅を健康に保つ |
| バスキングライト | 陸地を温め、体温調節をサポート |
| 水温調整用ヒーター | 冬場の低温対策として使用(25℃前後維持) |
| 陸地スペース(流木や浮島) | 甲羅干しをするために必要 |
| 餌(専用ペレット・野菜・小魚) | 栄養バランスの取れた食事を提供するため |
成体になると幼体よりも広いスペースが必要になり、水質管理もより重要になります。事前に必要なものをそろえ、適切な環境を整えましょう。
ミドリガメのおすすめの餌と与え方
ミドリガメの健康維持には、バランスの取れた食事が欠かせません。主食・副食・おやつを組み合わせて与えましょう。
① ミドリガメのおすすめの餌
| 餌の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 人工飼料(ペレット) | 栄養バランスが良く、主食に最適 |
| 野菜(小松菜・チンゲンサイ・ニンジン) | ビタミン補給に役立つ(レタスはNG) |
| 生餌(小魚・エビ・ミミズ) | たまに与えると食いつきが良い |
| カルシウム(カメ用サプリ・ボーン) | 甲羅や骨の強化に必要 |
② 餌の与え方のポイント
- 頻度:成体は1日1回または2日に1回
- 量:頭の大きさ程度が目安(与えすぎに注意)
- 食べ残しはすぐに取り除く:水質悪化を防ぐため
特に成体になると肥満になりやすいので、与えすぎに注意しましょう。また、栄養バランスの良い食事を心がけることが長生きの秘訣です。
ミドリガメの飼育禁止問題
ミドリガメはいつから飼育禁止?最新情報
ミドリガメ(ミシシッピアカミミガメ)は、2023年6月1日から**「条件付特定外来生物」**に指定されました。
これにより、2026年6月1日以降は、新たに飼育することが禁止されます。
現在の規制スケジュール
- 2023年6月1日:「条件付特定外来生物」に指定(販売・譲渡・輸入・放流が禁止)
- 2026年6月1日以降:新たな飼育も禁止(現在飼っている個体は引き続き飼育可能)
ただし、すでに飼っているミドリガメを手放すことは認められていないため、逃がさずに最後まで責任を持って飼育することが求められています。
ミドリガメが飼育禁止になった理由
ミドリガメが飼育禁止になった背景には、日本国内での深刻な生態系への影響があります。
① 日本の生態系への影響
ミドリガメは繁殖力が強く、全国の河川や池で野生化して在来種を圧迫しています。
- 在来のカメ(ニホンイシガメ・クサガメ)を駆逐
- 魚や水生昆虫の減少(捕食・競争による影響)
- 農作物や環境への被害(水田や堤防の破壊)
② 飼育放棄による野生化
ペットとして飼育されていたミドリガメの多くが、大きく育った後に飼育放棄され、河川や池に放流されてしまいました。その結果、全国で野生化が進み、問題が深刻化しました。
③ 国際的な外来種対策の強化
世界各国でも、外来種による生態系の破壊が問題視されており、日本でも外来生物の規制が強化されました。ミドリガメのように影響が大きい外来種は、早めに対策を講じる必要があると判断されたのです。
ミシシッピアカミミガメとの違いと規制の影響
ミドリガメは、実は「ミシシッピアカミミガメ」の幼体を指す通称です。つまり、ミドリガメとミシシッピアカミミガメは同じカメということになります。
そのため、今回の飼育禁止の対象はミドリガメ=ミシシッピアカミミガメであり、すべての個体が規制対象となります。
規制の影響
今回の規制により、以下のことが禁止されます。
- 2023年6月以降、新規の販売・譲渡・輸入・野外放流は禁止
- 2026年6月以降、新たな飼育が禁止(現在飼っている個体は飼育可能)
- 違反すると罰則の対象(罰金・懲役の可能性あり)
現在ミドリガメを飼っている方へ
規制後も適切に飼育を続けることが求められています。決して川や池に放さず、寿命を迎えるまで責任を持って世話をしましょう。
まとめ|ミドリガメ成体の飼育のポイント
ミドリガメ(ミシシッピアカミミガメ)は、成体になると最大30cm近くまで成長し、20~30年生きることもあるため、適切な飼育環境が必要です。室内で飼育する場合は、広い水槽・ろ過フィルター・紫外線ライト・バスキングスペースを整えることが重要です。
また、食事面では**バランスの取れた餌(ペレット・野菜・生餌)**を与え、適量を守ることで健康を維持できます。
ミドリガメの飼育禁止について
2023年6月1日より**「条件付特定外来生物」**に指定され、2026年6月1日以降は新たに飼育することが禁止されます。ただし、現在飼育しているミドリガメは引き続き飼育可能です。
ミドリガメを最後まで飼うために
ミドリガメは日本の生態系に影響を及ぼすため、絶対に野外に放してはいけません。最後まで責任を持って飼育し、適切な方法で見送ることが求められます。
ミドリガメの飼育は簡単ではありませんが、しっかりと環境を整えれば、長く一緒に過ごすことができます。ルールを守り、適切な飼育を心がけましょう!