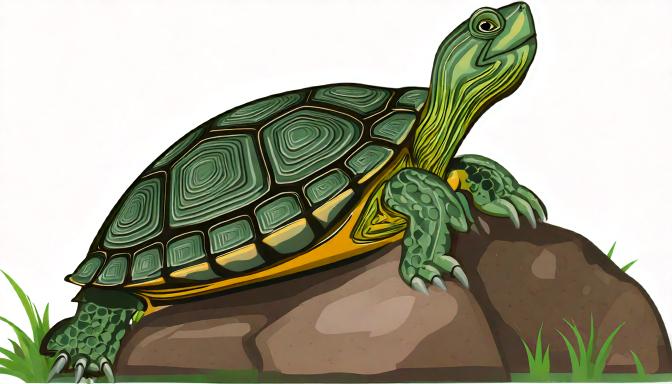川や池で甲羅干しをしている亀を見かけたことはありませんか?特に「ミドリガメ」は、日本各地の川でよく見られる外来種の亀として知られています。しかし、「ミドリガメは本来どこに生息するの?」「川にいる亀にはどんな種類がいるの?」と疑問に思う人も多いでしょう。
本記事では、ミドリガメをはじめとした野生の亀の生態や、川で見られる亀の種類、野生の亀を見つけたときの適切な対応について詳しく解説します。また、東京で亀を観察できるスポットや、ミドリガメが環境に与える影響についても触れていきます。
川で見つけた亀をどうすべきか迷っている方や、野生の亀に興味がある方は、ぜひ最後まで読んでみてください!
ミドリガメは川にいるのか?生息環境を解説
ミドリガメ(ミシシッピアカミミガメ)は、日本の川や池でよく見かける亀の一種です。本来は北米原産の外来種ですが、ペットとして輸入され、その後、飼い主によって放流された個体が野生化し、日本各地で定着しました。ここでは、ミドリガメの生息地や、日本の川にいる他の野生の亀について詳しく解説します。
ミドリガメの生息地:川や池に適応する理由
ミドリガメは、湖、池、沼、そして流れの穏やかな川に生息します。彼らが川でも生きられる理由は、以下のような特性によるものです。
- 適応力の高さ
ミドリガメは水質の悪化に比較的強く、都市部の川でも生息できるほどの耐久力を持っています。また、水温の変化にもある程度適応できるため、日本の気候にも馴染みやすいとされています。 - 雑食性でエサに困らない
ミドリガメは雑食性で、水草や小魚、昆虫、果実などを食べます。都市部の川でも食べ物を見つけやすく、生存しやすい環境が整っています。 - 冬眠して厳しい環境を乗り越える
冬になると、ミドリガメは水底の泥に潜り、冬眠することで寒さをしのぎます。これにより、比較的寒冷な地域でも生き延びることができます。
日本の川にいる野生の亀の種類
日本の川では、ミドリガメ以外にもさまざまな種類の野生の亀が生息しています。代表的な種類をいくつか紹介します。
- クサガメ(ニホンイシガメとの交雑種含む)
日本に昔から生息している在来種で、甲羅が黒っぽく、のど元に黄色い模様があるのが特徴です。ミドリガメとよく混同されますが、成長しても甲羅の色が緑色のままのミドリガメとは異なり、クサガメは黒っぽくなります。 - ニホンイシガメ
日本固有種の淡水ガメで、甲羅がやや平たく、黄色い斑点模様があります。近年は個体数が減少しており、ミドリガメやクサガメとの競争により生息域が縮小していると考えられています。 - スッポン
甲羅が硬くなく、柔らかい皮膚で覆われているのが特徴。肉食性が強く、小魚や甲殻類を積極的に捕食します。噛む力が強いため、川で見つけても不用意に触らないようにしましょう。
ミドリガメは強い繁殖力を持ち、日本の在来種と競争することで生態系に影響を与えているといわれています。そのため、野生のミドリガメを見つけた際は、在来種と区別することが重要です。
川で見かける野生の亀の特徴と見分け方
川で亀を見つけたとき、「これはミドリガメ?クサガメ?」と迷うことがあるかもしれません。日本の川には複数の亀が生息しており、それぞれ特徴が異なります。この章では、ミドリガメとクサガメの違いや、川で見かける亀の種類について詳しく解説します。
ミドリガメとクサガメの違いとは?
ミドリガメとクサガメは、どちらも川や池でよく見られる亀ですが、見た目や生態には大きな違いがあります。
| 特徴 | ミドリガメ | クサガメ |
|---|---|---|
| 甲羅の色 | 幼体は鮮やかな緑色、成長すると暗緑色~黒色に | 黒っぽい茶色、または暗緑色 |
| 顔の模様 | 目の後ろに赤い模様(アカミミガメの由来) | のど元に黄色い斑点がある |
| 生息環境 | 流れの緩やかな川、池、湖 | 川や池、農業用水路 |
| 食性 | 雑食性(植物、小魚、昆虫など) | 雑食性(ミドリガメよりもやや動物食寄り) |
| 原産地 | 北米(外来種) | 日本在来種 |
ミドリガメは輸入されたペットが野生化した外来種であるため、日本の在来種であるクサガメとは異なります。また、ミドリガメの目の後ろにある赤い模様は、クサガメにはない特徴なので見分けるポイントになります。
川にいる亀の種類:地域ごとの違い
日本の川には、ミドリガメやクサガメ以外にもさまざまな種類の亀が生息しています。地域によって生息する亀が異なるため、それぞれの特徴を知っておくと観察がより楽しくなります。
① 本州の川にいる亀
- ミドリガメ(外来種)
- クサガメ(在来種)
- ニホンイシガメ(在来種)
- スッポン(在来種)
本州では、ミドリガメが多く見られますが、在来種のクサガメやニホンイシガメも生息しています。ニホンイシガメは個体数が減少しているため、見つけたら貴重な存在です。
② 九州・四国の川にいる亀
- ミドリガメ(外来種)
- クサガメ(在来種)
- ニホンイシガメ(在来種)
- スッポン(在来種)
四国や九州では、本州と同じような種類の亀が生息していますが、暖かい地域ではミドリガメの繁殖が活発になりやすい傾向があります。
③ 沖縄・南西諸島の川にいる亀
- リュウキュウヤマガメ(在来種)
- セマルハコガメ(在来種・絶滅危惧種)
沖縄や南西諸島には、ミドリガメやクサガメのような一般的な淡水ガメのほか、リュウキュウヤマガメやセマルハコガメなど、地域特有の亀が生息しています。これらの亀は絶滅が危惧されており、見つけても捕まえたり持ち帰ったりしないようにしましょう。
亀がいる川の特徴と東京で見られるスポット
亀はどこにでもいるように見えますが、実は生息しやすい環境にはいくつかの条件があります。特に都市部では、生息できる川とそうでない川の差が大きいです。ここでは、亀が生息しやすい川の特徴や、東京で亀を観察できるスポットについて紹介します。
亀が生息しやすい川の条件とは?
亀が生息しやすい川には、いくつかの共通点があります。
① 流れが穏やかで水深が適度にある
ミドリガメやクサガメは、流れが速い川よりも流れが穏やかで浅瀬と深場が適度にある川を好みます。水流が強すぎると甲羅干しができる場所が少なくなり、エサも流されやすいため、亀にとっては過ごしにくい環境になります。
② 甲羅干しができる場所がある
亀は体温調節のために甲羅干しをする習性があります。そのため、大きな石や流木、人工的なコンクリートの縁など、日光を浴びられる場所がある川には亀が集まりやすくなります。
③ 餌となる生き物が豊富
ミドリガメやクサガメは雑食性で、水草や小魚、水生昆虫などを食べます。したがって、水生植物が繁茂していたり、小魚やエビが生息している川は、亀にとって理想的な環境です。
④ 人の影響を受けにくい
都市部の川では、コンクリート護岸が整備されていたり、水質が悪化している場所もあります。ある程度自然が残っている川や、水質が安定している川のほうが亀の生息に適している傾向があります。
亀がいる川【東京編】おすすめの観察スポット
東京都内でも、亀を観察できる川は意外と多く存在します。ここでは、東京で亀を見られるおすすめのスポットを紹介します。
① 石神井川(練馬区・板橋区など)
石神井公園を流れる石神井川は、都市部にありながら自然が豊かで、亀が生息しやすい環境が整っています。特に石神井公園内の池や、その周辺の川ではミドリガメやクサガメが甲羅干しをしている姿がよく見られます。
② 神田川(杉並区・中野区・新宿区など)
東京都内を流れる神田川も、場所によっては亀の姿を確認できます。特に井の頭恩賜公園の池周辺では、亀が多く見られるスポットとして有名です。
③ 目黒川(品川区・目黒区など)
桜の名所として有名な目黒川ですが、川沿いの静かなエリアでは**水面に浮かぶ亀を見かけることがあります。**特に流れが緩やかな場所では、甲羅干しをしている亀が観察できることも。
④ 荒川・隅田川(東京都東部)
荒川や隅田川の支流や護岸の一部では、亀が生息していることがあります。特に、河川敷に緑地が広がるエリアや、流れが緩やかな支流では、亀がのんびりと過ごしている様子が見られます。
⑤ 井の頭公園(武蔵野市・三鷹市)
公園内の池にはミドリガメやクサガメが多数生息しており、甲羅干しをしている姿がよく観察できます。ただし、池の環境保全のために亀の放流は禁止されているため、見つけても持ち込んだり、持ち帰ったりしないようにしましょう。
野生の亀を見つけたらどうする?適切な対応とは
川や池で亀を見つけると、「触ってもいいの?」「持ち帰って飼育してもいいの?」と迷うことがあるかもしれません。しかし、野生の亀には病気のリスクがあるほか、環境保全の観点からも安易に捕獲しないことが推奨されます。ここでは、野生の亀を見つけたときの適切な対応について詳しく解説します。
触ってもいい?野生の亀と病気のリスク
野生の亀は、一見するとかわいらしく見えますが、触る際には注意が必要です。
① 亀は細菌や寄生虫を持っている可能性がある
野生の亀の体表や甲羅には、サルモネラ菌などの細菌が付着している可能性があります。サルモネラ菌は人に感染すると、腹痛や下痢などの食中毒症状を引き起こすため、触った後は必ず手を洗うことが重要です。
また、亀の体内には寄生虫がいることもあります。特に川や池の水は人間にとって安全とは限らないため、触った手で目や口をこすらないように注意しましょう。
② 噛まれる危険性がある
スッポンなどの肉食性の強い亀は、鋭い歯と強い顎を持っているため、噛まれると大けがをする可能性があります。ミドリガメやクサガメも、警戒すると噛みつくことがあるため、無理に触らないほうが安全です。
③ ストレスを与えないように配慮する
野生の亀は、人に触られると強いストレスを感じます。捕まえたり、無理に動かしたりすると、亀の健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、基本的には観察するだけにとどめるのが望ましいです。
亀を見つけても連れて帰らないほうがいい理由
「野生の亀を見つけたから飼いたい!」と思う人もいるかもしれませんが、むやみに持ち帰ることは避けるべきです。
① 野生動物は飼育に向かない
野生で育った亀は、人間の手で飼育するのが難しい場合があります。特に、適切な環境(水温や日光、エサの種類など)を整えないと、健康を害してしまうことがあります。
② 外来種をむやみに飼うのはリスクが高い
ミドリガメは外来種であり、成長すると30cm近くになる個体もいます。ペットとして安易に飼育し始めると、大きくなったときに「飼いきれない」となり、再び自然に放流されるケースが後を絶ちません。しかし、ペットとして飼っていた亀を川や池に放すことは、法律で禁止されている場合があります。
③ 在来種の保護が必要
日本の川には、クサガメやニホンイシガメといった在来種が生息しています。外来種のミドリガメが増えすぎると、これらの在来種と競争し、結果的に在来の亀が減少することにつながります。そのため、「かわいいから」といって野生の亀を持ち帰ることは、生態系への悪影響を考慮すると避けるべきです。
まとめ:野生の亀を見つけたらどうすればいい?
✔ 観察するだけにとどめる(触る場合は手を洗う)
✔ むやみに捕獲せず、そのまま自然の中に残す
✔ 外来種(ミドリガメなど)をペットとして飼う前によく考える
野生の亀を見つけたら、持ち帰るのではなく、その場で観察し、自然のままにしておくのが最善の選択です。
ミドリガメが川に与える影響と問題点
ミドリガメ(ミシシッピアカミミガメ)は、もともと日本にはいなかった外来種です。しかし、ペットとして輸入された個体が捨てられたり、逃げ出したりして繁殖し、日本各地の川や池に定着しました。現在、ミドリガメの増加が生態系に与える影響が問題視されています。ここでは、ミドリガメが川に及ぼす影響や、環境問題について詳しく解説します。
ミドリガメの増加が日本の生態系に与える影響
① 在来種の亀との競争
ミドリガメは、クサガメやニホンイシガメなどの在来種とエサや生息地を巡って競争します。ミドリガメは繁殖力が強く、適応能力も高いため、在来の亀よりも生存競争で優位に立ちやすいといわれています。
特に、ニホンイシガメはもともと個体数が少なく、ミドリガメの増加によって生息域が狭まり、絶滅の危機に瀕していると指摘されています。
② 水生植物や小動物への影響
ミドリガメは雑食性で、水草や小魚、水生昆虫などを食べます。個体数が増えると、水辺の生態系全体に影響を与える可能性があります。
例えば、ミドリガメが増えることで
- 小魚や水生昆虫が減少する
- 水草が食べ尽くされ、水質の悪化を招く
といった問題が発生することがあります。
③ 人間への影響(農業・衛生面の問題)
ミドリガメが増えることで、人間にも間接的な影響が出ることがあります。
- 農作物への被害
ミドリガメは、稲や水辺の野菜を食べることがあり、田んぼや畑で農作物被害が報告されている地域もあります。 - 公園の池や川の水質悪化
ミドリガメが大量に生息していると、フンの量が増え、水質が悪化する原因になることがあります。特に都市部の公園では、**「亀が増えすぎて池の水が汚れやすくなった」**という問題も発生しています。
ミドリガメ問題の対策と駆除の取り組み
ミドリガメの増加を抑えるため、日本各地でさまざまな対策が進められています。
① 環境省による「条件付特定外来生物」指定
2023年6月、ミドリガメは「条件付特定外来生物」に指定されました。
これにより、
- 新たに輸入・販売することが禁止
- 飼育は可能だが、野外に放すことは禁止
という規制が設けられました。
今後、ミドリガメの流通が減ることで、野生化する個体の増加を防ぐ狙いがあります。
② 各自治体による駆除活動
一部の自治体では、ミドリガメの捕獲・駆除が行われています。
- 公園の池や湖での亀の捕獲
- 在来種との選別(クサガメやニホンイシガメは保護)
といった取り組みが進められています。
③ 飼い主の責任ある対応
ミドリガメの問題を解決するためには、**「飼い主が最後まで責任を持って世話をすること」**が最も重要です。
- 飼えなくなったからといって川や池に捨てない
- どうしても飼育できない場合は、自治体や専門団体に相談する
といった対応を心がけることが大切です。
まとめ:ミドリガメ問題のポイント
✔ 在来種との競争により、日本の生態系に影響を与えている
✔ 農業被害や水質悪化など、人間にも影響が出ることがある
✔ 「条件付特定外来生物」に指定され、輸入・販売は禁止
✔ 飼い主が最後まで責任を持って飼育することが重要
ミドリガメはかわいらしいペットですが、日本の川や池では外来種として問題視されています。
まとめ:ミドリガメと川の関係を正しく理解しよう
ミドリガメはもともと日本にいなかった外来種ですが、ペットとして輸入された個体が野生化し、全国の川や池で見られるようになりました。そのため、在来種との競争や水質悪化などの環境問題が発生しているのが現状です。
この記事では、ミドリガメと川の関係について、以下のポイントを解説しました。
① 亀が生息しやすい川の特徴とは?
✔ 流れが穏やかで水深が適度にある
✔ 甲羅干しができる場所がある
✔ 餌となる小魚や水生昆虫が豊富
東京にも、石神井川や神田川、井の頭公園など、亀を観察できるスポットがあります。
② 野生の亀を見つけたらどうする?
✔ 基本は観察だけにとどめ、無理に触らない
✔ 触った場合は必ず手を洗う(病原菌や寄生虫のリスクがある)
✔ 持ち帰って飼うのはNG! 外来種の増加が問題になっている
③ ミドリガメが川に与える影響とは?
✔ 在来種(クサガメ・ニホンイシガメ)との競争で生態系が崩れる
✔ 水草が食べ尽くされ、水質が悪化する
✔ 公園や農業環境への影響も懸念される
④ ミドリガメ問題の対策
✔ 2023年に「条件付特定外来生物」に指定され、輸入・販売は禁止に
✔ 一部の自治体では、ミドリガメの駆除を実施
✔ ペットとして迎えたら、最後まで責任を持って飼育することが大切!
川や池で亀を見つけたら、ただ「かわいい!」で終わらせず、その生態や環境への影響を正しく理解することが重要です。
ミドリガメは、ペットとしての魅力もありますが、日本の自然環境では問題を引き起こしている外来種でもあります。川で亀を見つけたら、むやみに捕まえたり持ち帰ったりせず、適切な観察マナーを守ることが大切です。
今後、私たちができることは、
✅ 自然の生き物を正しく観察し、生態系を大切にすること
✅ ペットとして迎えるなら、最後まで責任を持つこと
こうした意識を持つことが、日本の川の環境を守る第一歩になります。